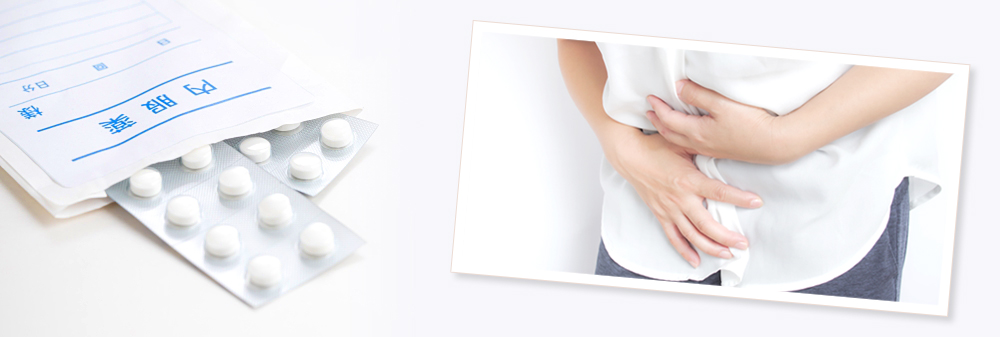- 腸活
便秘の種類には何がある?各タイプの原因と予防法とは
「毎日すっきりしない」「お腹が張ってつらい」など、便秘に悩む方は少なくありません。しかし、便秘症と一口に言っても、原因や症状は人によってさまざまで、対応方法も異なります。間違った対策を続けると、かえって症状を悪化させる場合もあるため、まずは自分の便秘タイプを正しく知ることが便秘解消には重要です。
当記事では、便秘の定義や種類、各タイプの原因と症状、予防法について詳しく解説します。日常生活の中で実践できる予防策を取り上げていますので、便秘に悩む方や予防を考えている方は最後までご覧ください。
1.便秘とは?
便秘とは、「本来体外に排出すべき糞便を、十分量かつ快適に排出できない状態」を指します。日本国内の診療ガイドラインでは、排出量と排出の快適性の両方に着目した定義が採用されています。また、海外でも便秘は「排便困難・頻度の低下・残便感などの症状を伴う症候群」とされており、内容的には日本の定義とほぼ共通です。
そのため、便秘には単に排便回数が少ないだけでなく、排便の際の不快感や困難、肛門まわりの違和感も含まれます。こうした基準を踏まえると、便秘は日常的な不快症状だけでなく、生活の質にも影響する重要な健康課題と言えるでしょう。
2.【便秘の種類別】原因と症状
便秘にはいくつかの種類があり、それぞれ原因や発症の仕組みが異なります。ここでは、代表的な4つのタイプに分けて、原因や主な症状を説明します。
2-1.機能性便秘
機能性便秘とは、大腸に形態的な異常がないにもかかわらず、排便機能に障害が生じて起こる便秘です。原因や症状に応じて「大腸通過遅延型」「大腸通過正常型」「機能性便排出障害」の3つに分類されます。
大腸通過遅延型では、便の移送に時間がかかるため排便回数が著しく減少し、腹部膨満感や不快感を訴えることが多くみられます。一方、大腸通過正常型は、腸の動きに問題はないものの、食事量や食物繊維の不足などにより排便量が少なくなり、結果として排便回数減少となるタイプです。機能性便排出障害では、直腸や骨盤底筋の機能低下によってスムーズに排便できず、強い排便困難感や残便感が現れます。
2-2.器質性便秘
器質性便秘とは、大腸や直腸に腫瘍や炎症などの形態的異常がみられる便秘です。内視鏡検査やCT、X線などの専門的検査が必要とされ、原因に応じて「狭窄性」と「非狭窄性」に分類されます。
狭窄性は、大腸がんや炎症性腸疾患などによる腸管の物理的な狭まりで、便秘に加えて腹痛・血便などの症状を伴うことがあります。一方、非狭窄性では大腸の異常な拡張や直腸の変形などが原因で、便の通過や排出がうまくいかず、排便回数の減少や残便感がみられるのが特徴です。たとえば、巨大結腸症や直腸瘤などが該当し、専門的な診断と治療が求められます。
2-3.症候性便秘
症候性便秘はほかの病気に伴って起こる便秘で、内分泌代謝疾患や神経・筋疾患、膠原病などの影響によって腸の機能が低下することで発症します。たとえば、甲状腺機能低下症や副甲状腺機能亢進症では大腸のぜん動運動が鈍くなり、便の移動が遅れて便秘を引き起こします。
また、糖尿病やパーキンソン病などで神経の働きが障害されると、排便に必要な腸の動きや筋力が十分に発揮されず、慢性的な便秘につながる場合があります。女性の場合はホルモンやストレスの影響で生理前や妊娠中に一時的に便秘が起こることもあり、症候性便秘の一種と考えられています。
2-4.薬剤性便秘
薬剤性便秘は、服用薬の影響で腸の動きが低下し、排便が困難になる副作用による便秘です。抗うつ薬や抗コリン薬、向精神薬、パーキンソン病治療薬、鎮咳薬(リン酸コデイン)などには、大腸のぜん動運動を抑える作用があり、便の移動が遅れてしまいます。
また、アルミニウムを含む制酸薬やカルシウム拮抗薬、利尿薬なども便秘を引き起こしやすい薬の一例です。バリウム検査後や下剤を習慣的に使用している場合も、腸の働きが鈍くなって便秘につながることがあります。
3.便秘の予防方法
便秘は、食事や運動など日常の生活習慣を見直すことで、予防や改善が期待できます。ただし、長期間続く場合や症状が重い場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。ここでは、便秘の基本的な予防法を紹介します。
3-1.こまめな水分補給を意識する
水分摂取が不足すると、便の水分量が減り、硬くなって排出しづらくなります。水分をしっかりとることで便のかさが増し、腸を刺激して排便を促す効果が期待できます。目安として、今よりコップ2杯分(約400ml)多く飲むことを心がけてみましょう。
特に起床時の1杯は、腸のぜん動運動を活性化させるのに有効です。また、寝る前に水分を飲むことで睡眠中の脱水予防にもなります。のどの渇きを感じにくい方や食事量が少ない方、高齢者の方は、水分が不足しやすいため注意が必要です。カフェインを含まない水やお茶、白湯などをこまめに取り入れ、日常的に水分補給の習慣をつけることが便秘予防につながります。
3-2.食物繊維を積極的に摂取する
食物繊維は、腸のぜん動運動を促進し、便の量を増やしてスムーズな排便を助ける働きがあります。厚生労働省の目標摂取量は、成人男性で1日20g以上、女性で18g以上ですが、実際の平均摂取量はそれを大きく下回っていると言われています。
まずは、1日3~4gの摂取増加を目指し、小鉢料理を2品追加するなど、手軽に始めましょう。野菜に加え、果物や海藻、豆類、きのこ類などをバランスよく取り入れるのがおすすめです。水溶性食物繊維は便を柔らかくし、不溶性食物繊維は便のかさを増やす役割がありますが、重度の便秘の方は不溶性食物繊維の摂りすぎに注意が必要です。食事量が少ない方は、ファイバー粉末や粉寒天などの活用も効果的です。
3-3.腸内環境を整える食品を取り入れる
腸には多種多様な腸内細菌が存在し、善玉菌を増やすことで腸の働きが活発になります。たとえば、ヨーグルトや納豆、味噌、キムチなどの発酵食品には善玉菌が含まれており、継続的に摂ることで腸内のバランスを整える助けになります。
また、善玉菌のエサとなる食材としては、オリゴ糖や食物繊維が挙げられ、野菜や果物、海藻などに豊富です。これらを組み合わせて取り入れることで、腸内フローラの環境が整い、自然な排便が促されます。毎日の食事にオリゴ糖を取り入れるには、普段の甘味料の代わりにオリゴ糖を使う方法がおすすめです。「オリゴのおかげ」は使いやすいシロップタイプの甘味料なので、普段の食事に簡単に取り入れることができます。
3-4.適度な運動を心がける
運動不足により腹筋が弱ると腸のぜん動運動が低下し、便秘を招きやすくなります。排便時には腹圧も必要になるため、腹筋を鍛えることで排便力を高める効果が期待できます。1日20~30分程度のウォーキングや軽いストレッチ、ヨガなどの全身運動を取り入れてみましょう。
また、腸を外から刺激する「の」の字マッサージを毎日の習慣に取り入れるのもおすすめです。入浴中や就寝前など、リラックスした時間に行うと続けやすくなります。無理のない範囲で、毎日の生活に適度な運動を取り入れることが便秘対策の基本です。
まとめ
便秘症状は、単なる排便の不調ではなく、全身の健康状態を映し出すサインでもあります。機能性や器質性、ほかの病気や薬に起因する便秘など、便秘の種類によって原因や対処法は異なります。まずは、自分の便秘タイプを把握しましょう。
その上で、水分補給や食物繊維の摂取、腸内環境を整える食品の選択、日常的な運動を取り入れることが、便秘の予防や改善につながります。症状が長引く場合や悪化した場合は、医師に相談することも大切です。生活の質を落とさないためにも、今日からできる対策を1つずつ始めてみましょう。

<プロフィール>
加勢田 千尋
一般社団法人日本腸内環境食育推進協会代表理事、管理栄養士。病院・企業にて7000人以上の栄養指導・食事アドバイスを行う。独立後、腸に特化した食育講座『腸の学校®』を監修•運営する。自身も幼い頃からアトピーや腸の不調に悩まされ続け、腸内環境を整える食事法により便秘やアトピーなどの不調を3カ月で卒業。 現在は薬やサプリメントに頼らないずぼら腸活を伝えている。