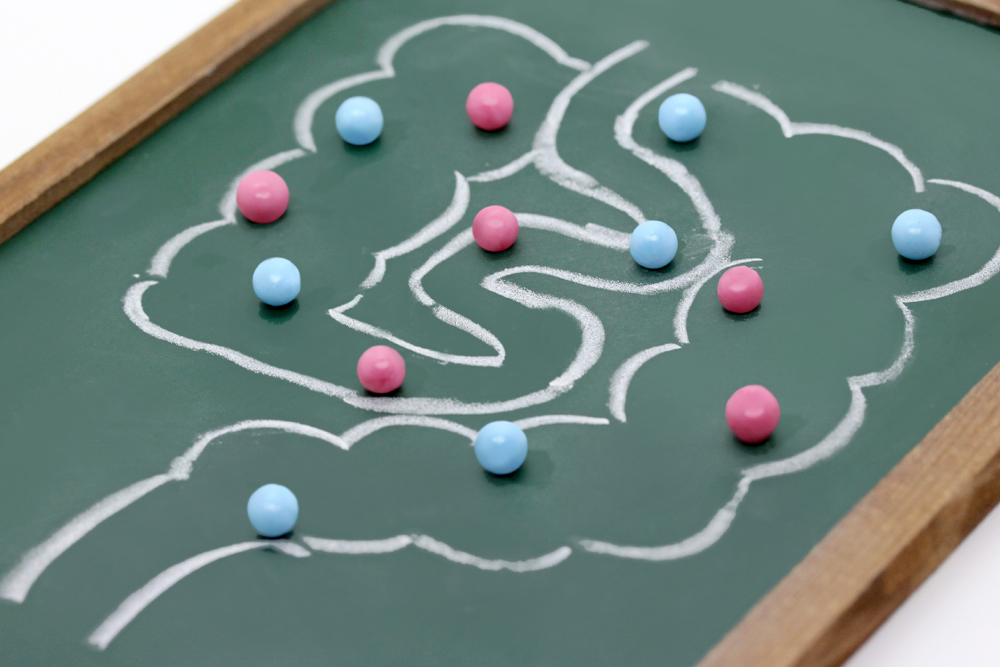- 腸活
善玉菌とは?悪玉菌との違いや腸内環境の整え方を分かりやすく解説
腸内環境の乱れによって、便秘や肌荒れ、免疫力の低下など、さまざまな不調を感じている方は少なくありません。体調の乱れの背景には「善玉菌」と「悪玉菌」のバランスが大きく関わっており、特に善玉菌は年齢や生活習慣によって減少しやすいため、意識的に摂取することが求められます。
当記事では、善玉菌とは何かを基礎知識から解説し、悪玉菌との違いや、腸内フローラを整える方法、日常生活に取り入れやすい食習慣やレシピを紹介します。腸内環境を改善し、健康な毎日を目指したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
1. 善玉菌とは
「善玉菌」とは、腸内細菌の中でも人体に有益な働きをする菌の総称です。代表的なものにビフィズス菌や乳酸菌があります。善玉菌は腸内で糖分や食物繊維を発酵させて乳酸や酢酸をつくり、腸内を弱酸性に保つことで、悪玉菌の繁殖を抑える役割を担っています。
善玉菌が優勢な腸内環境では、病原菌の侵入を防ぎ、免疫機能を維持・向上させる効果が期待されます。一方で、善玉菌は腸内に長く定着しにくいため、継続的に食事などから摂取する必要があります。健康な腸内フローラの理想は、善玉菌2割・悪玉菌1割・日和見菌7割とされており、日々の生活習慣がそのバランスに影響します。
1-1. 腸内環境に関わる腸内フローラとは
腸内フローラとは、腸内に棲む約1,000種・100兆個もの細菌がバランスを保ちながら共生している状態のことです。細菌の密集した様子がお花畑(flora)のように見えることから名づけられました。正式には「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」と呼ばれます。
腸内フローラは「消化を助ける物質を生み出す」「免疫機能を高める」「健康維持に関わる」などの役割を担っています。腸内フローラの細菌群は善玉菌・悪玉菌・日和見菌に分類され、それぞれのバランスによって腸内環境が左右されます。中でも善玉菌が優勢な状態が健康的とされており、「腸活」は腸内フローラを整えるための習慣の1つです。
1-2. 善玉菌と悪玉菌・日和見菌の違い
腸内には「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」の3種類が存在し、それぞれ異なる働きをしています。善玉菌はビフィズス菌や乳酸菌などで、消化吸収を助けたり、免疫力を高めたりして健康をサポートする菌です。悪玉菌はウェルシュ菌やブドウ球菌などがあり、腸内を腐敗させ、有害物質やガスを発生させる原因になります。日和見菌は、健康状態や腸内環境の優劣によって、善玉菌・悪玉菌いずれかの働きに傾く性質を持っています。
| 分類 | 主な菌種 | 主な働き |
|---|---|---|
| 善玉菌 |
|
|
| 悪玉菌 |
|
|
| 日和見菌 |
|
|
2. 善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れるとどうなる?
食生活の乱れやストレス、加齢などにより悪玉菌が増加すると、腸内フローラのバランスが崩れ、さまざまな体調不良を引き起こすリスクが高まります。悪玉菌は腸内でアンモニアやインドールなどの有害物質を生成し、腸に炎症をもたらすだけでなく、有害物質の毒素が血液に入り込んで全身に悪影響を与えることもあります。さらに、免疫機能の低下や生活習慣病の悪化、肌トラブル、精神的な不調など、腸内環境の悪化が全身の健康と深く関わっていることが判明しています。
<腸内フローラのバランスが乱れることで起こる不調の例>
- 便秘、下痢などの消化器症状
- おならや便の悪臭
- 免疫力の低下による感染症リスクの増加
- 肌荒れや吹き出物
- アレルギー症状の悪化
- イライラ、不安感など精神面の不調
- 肥満や糖尿病など、生活習慣病の進行
腸内環境の乱れは、単なるおなかの不調にとどまらず、全身の健康に波及する問題です。そのため、日頃から腸内フローラを整える意識が求められます。
3. 主な善玉菌の種類
腸内フローラには多種多様な細菌が共生していますが、中でも健康維持に役立つとされるのが「善玉菌」です。ここでは、代表的な善玉菌の種類を紹介します。
3-1. ビフィズス菌
ビフィズス菌とは、腸内に多く棲む善玉菌の一種で、整腸作用や免疫力の維持に貢献する細菌です。大腸では、善玉菌のうち約99%がビフィズス菌とされており、腸内フローラの健康を保つ上で中心的な存在です。ビフィズス菌は食物繊維やオリゴ糖をエサにして酢酸などの短鎖脂肪酸を生成し、腸内を弱酸性に保つことで悪玉菌の繁殖を抑えます。
また、ミネラルの吸収促進やアレルギーの抑制など、全身の健康への影響も注目されています。乳児期は特に多く、母乳に含まれるオリゴ糖がビフィズス菌の増殖を助けています。しかし、ビフィズス菌は加齢とともに減少するため、食事やサプリメントなどで継続的に補うことが大切です。
3-2. 乳酸菌
乳酸菌とは、糖を発酵させて乳酸をつくる微生物の総称で、腸内環境を整える働きを持つ善玉菌の1つです。体内では悪玉菌の増殖を抑えることで腸内フローラのバランスを整え、便通の改善や免疫力アップなどに役立ちます。自然界にも広く存在し、ヨーグルトやチーズ、漬け物、日本酒などの発酵食品の製造にも使われていることで知られています。
乳酸菌はビフィズス菌と混同されがちですが、分類学上は異なる菌で、生息場所や働きにも違いがあります。ビフィズス菌が主に大腸に生息し、酢酸なども産生するのに対し、乳酸菌は酸素がある環境でも生息でき、主に乳酸のみを生成するのが特徴です。そのため、人や動物の腸内だけでなく、土壌や空気中などにも乳酸菌は存在します。
3-3. 酪酸菌
酪酸菌とは、大腸に棲む善玉菌の一種で、腸内環境を整える「酪酸」を産生する腸内細菌です。酪酸は、腸内を弱酸性に保って悪玉菌の増殖を抑えたり、大腸の粘膜を保護したりする働きを持つ短鎖脂肪酸の1つです。一部の酪酸菌は「芽胞(がほう)」という殻に包まれているため、胃酸や熱、抗生物質にも強く、生きて腸に届きやすいという特性があります。
また、酪酸は腸のぜん動運動の促進や、免疫機能を調整する制御性T細胞の活性化にも関与していることから、近年、酪酸菌は「スーパー善玉菌」として注目を集めています。ただし、酪酸菌は酸素に弱く、大腸以外では活動しづらいため、食事から摂取するにはサプリメントなどの併用が効果的です。
4. 善玉菌を増やすメリット
善玉菌の数を増やすことで、腸内環境が整い、全身の健康にさまざまな好影響をもたらします。ここでは、善玉菌を増やす具体的なメリットを詳しく解説します。
4-1. 悪玉菌の繁殖を抑える
食生活の乱れやストレス、加齢などで善玉菌が減ると、悪玉菌が優勢になりやすく、有害物質の産生によって便秘・肌荒れ・疲労感・アレルギーの悪化などの不調を引き起こす恐れがあります。そこで善玉菌を増やすと、腸内を弱酸性に保ち、悪玉菌の繁殖を効果的に抑えることができます。
悪玉菌はアルカリ性の環境を好むため、善玉菌がつくる酢酸や酪酸などの短鎖脂肪酸によって腸内が酸性に傾くと、活動が制限されます。この働きにより、腸内フローラのバランスが整えば、便通の改善や肌の調子の向上、免疫力の維持にもつながります。善玉菌を増やすことは、悪循環を断ち切る第一歩と言えるでしょう。
4-2. 免疫の働きを助ける
腸は免疫細胞の約7割が集まると言われる免疫の要であり、小腸には異物を感知・排除するパイエル板というリンパ組織が存在しています。一方、大腸では善玉菌が作り出す酢酸や酪酸が腸内を弱酸性に保ち、病原菌の侵入を防ぐバリア機能を高めます。
さらに、酪酸には炎症やアレルギー反応を抑制する「制御性T細胞」を増やす作用もあり、適切な免疫反応を維持する上で欠かせないものです。善玉菌を優勢に保つことは、感染症やアレルギーから身を守るための免疫強化策と言えるでしょう。
4-3. 腸のぜん動運動を促す
善玉菌を増やすことは、腸のぜん動運動を活性化し、自然な排便を促す上で重要です。乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌は、腸内で糖を分解して乳酸や酢酸をつくり、腸内環境を酸性に保ちます。酸性環境が大腸を適度に刺激し、ぜん動運動を促進して便をスムーズに移動させることで、便秘の予防・改善を図れる可能性があります。
また、酪酸菌が産生する酪酸は、大腸上皮細胞のエネルギー源であり、腸粘膜の健康維持やバリア機能に貢献します。腸の健康と快適な排便を維持するには、日々の食事で善玉菌を意識的に摂取することがポイントです。
4-4. 一部のビタミンを生み出す
善玉菌の中には、身体に必要なビタミンの一部を生み出す働きを持つ菌も存在します。特にビフィズス菌などは、ビタミンB1・B2・B6・B12・葉酸・ビタミンKなどの合成に関与し、大腸内で栄養素を生成します。
ビタミンは、代謝や神経の健康、免疫機能の維持などに欠かせない栄養素です。不足すると肌荒れや疲労感、貧血などの不調を引き起こすこともあります。大腸で合成されたビタミンの一部は、大腸からも吸収され、わずかながら栄養に貢献していると考えられています。
5. 善玉菌を増やす方法
善玉菌を増やす方法には、菌そのものを摂る「プロバイオティクス」、そのエサを与える「プレバイオティクス」、両方を組み合わせた「シンバイオティクス」の3つがあります。ここでは、それぞれの言葉の意味についてより詳しく説明します。
5-1. プロバイオティクス
プロバイオティクスとは、生きたまま腸に届き、健康によい作用をもたらす微生物のことを指します。乳酸菌やビフィズス菌などが代表的です。腸内フローラのバランスを整えることで、便秘や下痢の改善、免疫機能のサポート、感染症予防などの効果が期待されています。プロバイオティクスとして有効とされるのは、胃酸や胆汁に耐えて腸まで届き、腸内で一定量が生きて働くことが研究などで科学的に証明された特定の菌株に限られます。
こうした善玉菌の活動を支える栄養源として重要なのが「オリゴ糖」です。オリゴ糖は消化されずに大腸まで届き、ビフィズス菌などの善玉菌の増殖を促すことで、プロバイオティクスの効果をより高めます。
5-2. プレバイオティクス
プレバイオティクスとは、善玉菌の栄養源となり、その増殖を助ける食品成分のことです。
プロバイオティクスが「菌そのもの」であるのに対し、プレバイオティクスは「菌のエサ」となる成分で、消化されずに大腸まで届き、ビフィズス菌などの善玉菌を選択的に増やす働きがあります。フラクトオリゴ糖・ガラクトオリゴ糖・乳糖果糖オリゴ糖などの難消化性オリゴ糖や、イヌリンなどの食物繊維が代表的な成分です。
その中でも、難消化性オリゴ糖はビフィズス菌の増殖に効果的で、腸内フローラを整える手助けをします。プレバイオティクスの摂取により、整腸作用やミネラル吸収の促進、免疫機能の向上など、さまざまな健康効果が期待されています。
5-3. シンバイオティクス
シンバイオティクスとは、善玉菌(プロバイオティクス)とその栄養源(プレバイオティクス)を一緒に摂ることで、腸内環境をより効果的に整える方法です。プロバイオティクスだけでなく、オリゴ糖や食物繊維などのプレバイオティクスも同時に摂ることで、善玉菌の増殖と働きをサポートできます。
たとえば、ヨーグルトとバナナ、納豆とおくらなど、身近な食材の組み合わせで、簡単にシンバイオティクスを実践することは可能です。このように菌とエサの両方をバランスよく取り入れることは、腸内フローラのバランスが安定し、便通の改善や免疫力の強化など、全身の健康維持にもつながるでしょう。
6. 善玉菌を増やすレシピ
善玉菌を増やすには、日々の食事に工夫を取り入れることが大切です。ここでは、シロップタイプの甘味料「オリゴのおかげ」を使った、腸内環境を整えるのに役立つレシピを紹介します。
6-1. 腸活玉
「腸活玉」は、腸内環境を整える食材を手軽に摂れるインスタント味噌汁の素です。味噌・かつお節・白すりごま・「オリゴのおかげ」を混ぜて丸めた味噌玉で、お湯を注ぐだけで本格的な味噌汁が完成します。冷蔵で10日間、冷凍なら1か月間保存できるので、忙しい朝や小腹が空いたときにも便利です。
<材料(10個分)>
味噌:150g
かつお節:15g
白すりごま:40g
オリゴのおかげ:80g
<作り方>
Step1:混ぜる
ボウルにすべての材料を入れ、よく混ぜ合わせます。
Step2:丸める
10等分にして、ラップなどで丸めて保存します。
Step3:味噌汁をつくる
味噌玉1個を汁椀に入れ、お湯140ccを注いでよくかき混ぜれば完成です。
6-2. 鮭のちゃんちゃん焼き
「鮭のちゃんちゃん焼き」は、野菜やきのこに含まれる食物繊維と、「腸活玉」に含まれるオリゴ糖や乳酸菌を一緒に摂れる腸活レシピです。クッキングシートで包んで蒸し焼きにすることで、栄養と旨味を閉じ込めながら手軽に調理できます。
<材料(2人分)>
鮭:2切れ
キャベツ:20g
にんじん:1/4本
ピーマン:1個
しめじ:20g
腸活玉:2個
みりん:小さじ1
バター:10g
<作り方>
Step1:下ごしらえをする
キャベツは一口大に、にんじんは短冊切り、ピーマンは千切り、しめじは小房に分けておきます。
Step2:タレをつくる
腸活玉とみりんを混ぜてタレを作ります。
Step3:具材を包む
クッキングシートの中央に鮭をのせ、2のタレを塗ります。1の野菜を上に乗せ、しっかりと包みます。
Step4:味つけをする
フライパンに3を入れ、水100mlを加えて蓋をし、中火で10分加熱します。
Step5:仕上げる
加熱後、鮭の上にバターを乗せて余熱で溶かせば完成です。
6-3. ジンジャーミントティー
ミントとレモンのさわやかな味で暑い日にもごくごく飲めるドリンクです。ペパーミントに含まれるメントールには腸管の筋肉を弛緩させる作用があり、おなかのハリや不快感の解消が期待できます。冷たい飲み物でおなかの冷えが気になる方は、しょうがを多めに入れるなどお好みで調整してください。
<材料(500ml分)>
ペパーミントティー(ティーバック):1個
お湯:400ml
水:100ml
オリゴのおかげ:大さじ1~2
レモン果汁:大さじ1~2
しょうが(チューブ入り):1~2cm
<作り方>
Step1:抽出
400mlのお湯にティーバッグを入れ、ミントティーを抽出します。
Step2:オリゴのおかげを加える
ティーバッグを取り除き、オリゴのおかげ、レモン果汁、しょうがを加えてよく混ぜます。
Step3:水を加える
水100mlを加え、かき混ぜます。
(粗熱が取れたら冷蔵庫で保存し、できるだけ1日で飲み切ってください。)
まとめ
善玉菌は、腸内環境を整えるだけでなく、免疫力の向上や便通の改善など、健康にさまざまな恩恵をもたらす重要な存在です。特にビフィズス菌や乳酸菌、酪酸菌などの善玉菌を日常的に摂取することで、腸内バランスが整い、全身の不調改善や予防を図れます。
また、善玉菌そのものを摂る「プロバイオティクス」や、善玉菌のエサとなる「プレバイオティクス」、そして両方を組み合わせた「シンバイオティクス」の実践が、善玉菌を増やすカギとなります。記事内で紹介したレシピや方法を取り入れ、健康的な毎日を目指しましょう。

<プロフィール>
加勢田 千尋
一般社団法人日本腸内環境食育推進協会代表理事、管理栄養士。病院・企業にて7000人以上の栄養指導・食事アドバイスを行う。独立後、腸に特化した食育講座『腸の学校®』を監修•運営する。自身も幼い頃からアトピーや腸の不調に悩まされ続け、腸内環境を整える食事法により便秘やアトピーなどの不調を3カ月で卒業。 現在は薬やサプリメントに頼らないずぼら腸活を伝えている。